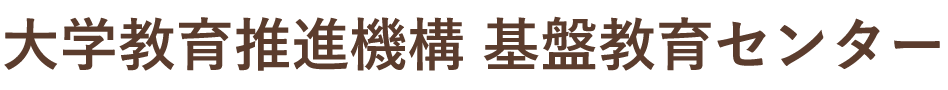総合系科目
野外調査論/Methodology of Fieldwork
- 担当教員名 西尾 孝佳(雑草管理教育研究センター)
- 学期・曜日時限 前期 水曜7-8時限
- 時間割コード G800235
- 単位数 2
- 授業の内容
社会科学,自然科学を問わず,どんな分野でも,町や自然の中に出かけ,自らの手足でデータを集める必要に迫られるかもしれません。この授業ではその手法と考え方を,野外調査の実践を通じて学びます。
環境マネジメント実践/Environmental Management Practice
- 担当教員名 横尾 昇剛(地域デザイン科学部)
- 学期・曜日時限 通年 不定時
- 時間割コード G845100
- 単位数 2
- 授業の内容
宇都宮市役所の環境対策の実施状況を実地で監査します。宇都宮市役所は現在ISO14001という国際規格に基づいて環境マネージメントシステムを構築し、それを実施しています。それが約束通りに実施されているかを学生が監査します。
学生は2名程度のチームを組んで市役所の「課」などの部署に訪問して、書類のチェックと実地の観察を行い、環境マネージメントシステムとの整合性について考察します。この監査は「練習」といった性格ではなく、宇都宮市役所の「環境マネージメントシステム」に組み入れられた実質的な活動です(ですから市役所に対して「守秘義務」を負います)。
監査実務までに演習を繰り返して、ISO14001の仕組みの理解を深めるとともに、監査のシミュレーションを行って、自信をもって参加できるようにします。
宇大生の宇大生による宇大生のための理想の授業/The Ideal Class of Udai Students, by Udai Students, for Udai Students
- 担当教員名 石井 和也(基盤教育)
- 学期・曜日時限 前期 集中
- 時間割コード G845150
- 単位数 2
- 授業の内容
【本授業は9月の集中講義として開講する予定です。詳細は教務ポータル等でお知らせします。また,本授業のTwitterアカウント(@risou_no_jyugyo)でも情報を発信していますのでぜひご覧ください】
本授業は「学生発案型授業」です。本授業の昨年度受講生と有志学生がSA(Student Assistant)となり,授業テーマや授業のやり方を主体的に発案し,教員と協働して授業準備を進めてきました。この授業では,授業当日の進行も学生自身が担います。SAは,授業でディスカッションしたいテーマを予め入念に調査し,授業当日は話題提供者として受講生に自らの考えを披露します。受講学生は,SAが提示したテーマや考えにについて自らの考えをまとめるとともに,SAとともにディスカッションを繰り返します。このことを通じ,本授業は,学生(SA)と学生(受講生)とがともに意見を交わすことで,示されたテーマについて理解を深めるだけではなく,他者の考えを知り自らの視野を広げ,その先の自主的な学びの探求への足がかりを得ることを期待しています。
なお,本授業では容易に答えが出るようなテーマは扱いません。SAが真剣に格闘し続けてきた「難しい問い」について,SAと受講生が一丸となり徹底的にディスカッションすることになるでしょう。答えをすぐ求めるのではなく,「難しい問い」に挑むためのアプローチを学びながら,こうした挑戦の面白さを実感して欲しいと思います。
大学論~高大接続について考える~/The theory of a university
- 担当教員名 大竹 洋平(教育学部)
- 学期・曜日時限 後期 火曜9-10時限
- 時間割コード G845160
- 単位数 2
- 授業の内容
この授業では、高大接続改革(高校教育・大学入学者選抜・大学教育の三位一体の改革)について考えます。資料の読解・議論等を通して、最新事情を把握し、学生さん自身の今後の生涯学習に活かせることを目指します。発表・議論を中心とした授業にする予定です。
青年期教育論~教育心理の専門職として~/The education of youth
- 担当教員名 大竹 洋平(教育学部)
- 学期・曜日時限 前期 月曜9-10時限
- 時間割コード G845170
- 単位数 2
- 授業の内容
この授業では、教育・心理分野の専門職について、人材育成・資格制度・キャリアなどを考えます。資料の読解・議論等を通して、最新事情を把握し、学生さん自身の今後の生涯学習に活かせることを目指します。発表・議論を中心とした授業にする予定です。
実践・宇都宮のまちづくり/Introduction to Utsunomiya City Government
- 担当教員名 馬場 将広(その他)
- 学期・曜日時限 前期 水曜7-8時限
- 時間割コード G845180
- 単位数 2
- 授業の内容
人口減少や高齢化などによる地域社会の変容に対応した持続可能なまちをつくるために、宇都宮市がどのような政策を立案・実行しているのかを、市職員が実体験を交えながら講義します。データや情報と実社会での行政活動との融合を理解するアクティブ・ラーニング科目です。最終回には、宇都宮市長がまちづくり全般について授業を行う予定です。ただし,新型コロナウィルス感染症の状況等により本授業のすべてまたは一部をオンラインに変更した場合は授業内容について変更になる場合があります。
※※宇都宮市職員(公務員)を目指す方には,特におすすめです※※
地域金融論~現役金融パーソンとエコノミストが語る、地域経済の現状と地域金融機関の役割~/Financial Theory and the Regional Bank
- 担当教員名 新村 健司(その他)
- 学期・曜日時限 前期 月曜3-4時限
- 時間割コード G845205
- 単位数 2
- 授業の内容
経済や金融の基礎知識、日本経済の現状・課題を学習した上で、栃木県を中心とした地域経済の課題や活性化策について考えるアクティブ・ラーニング科目です。明治28(1895)年創業の「足利銀行」の歴史や、地域金融機関の役割を通じて見える地域経済の今日的な課題など、実学を幅広く取り上げることを予定しています。
地域金融機関とともに「地方創生」を考える/Regional Revitalization Promoted by Local Bank
- 担当教員名 市田 治雄(その他)
- 学期・曜日時限 前期 オンデマンド科目
- 時間割コード G845210
- 単位数 2
- 授業の内容
我が国全体が急速な人口減少と高齢化を迎えようとしている中、栃木銀行は、平成27年2月に「とちぎん地域産業創生プログラム」を展開し、地方創生に対する取組みを行って来ました。地域金融機関として地域のさまざまな課題解決のために、地域資源を活用した地域独自の地方創生についての当行の取組みを、事例を交えて講義します。当行地域創生室とともに、実社会に提案できる課題解決策について一緒に考えていくアクティブ・ラーニング科目です。
3.11と学問の不確かさ/3.11 and Uncertainty of Our Study
- 担当教員名 清水 奈名子(国際学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜9-10時限
- 時間割コード G845223
- 単位数 2
- 授業の内容
2011年3月11日14時46分18秒に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波、東京電力福島第1原子力発電所の事故は。東日本大震災(3.11)として未曾有の災害を日本と世界にもたらしました。この東日本大震災は、学問の在り方についても多くの問題を提起しています.しかしながら、震災から11年目となる現在にいたるまで,この震災と原発事故をどのように考えるのか、そして日本と世界は何を学ぶべきなのかについて、「専門家」が異なる見解を示してきました.
この不確かで混乱している震災後の状況をまず理解することが,今後の学問の在り方について、そして大学における学びをめぐる議論の出発点になるのではないでしょうか。そもそも学問的な理論や研究成果は、一定の条件のもとで選択された「仮説」であることが多く、本質的に不確実性を抱えています。さらに研究成果が社会で利用される際にも,その実施方法や評価基準は多様であり、当事者との関係性や時代とともに変化しうるものです。
この授業では、確固とした体系をもつと考えられている学問の「不確かさ」に注目し、この共通テーマについて多様な学部、センターの教員が異なる分野から考察することで,3.11後の大学における学びについて考えることを目的としています.なお,本授業はアクティブ・ラーニング科目です.
食と生命のフィールド実践演習/Field Practice of Food, Environment and Life
- 担当教員名 長尾 慶和(農学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜5-8時限
- 時間割コード G845231
- 単位数 4
- 授業の内容
附属農場における実習と関連する事前学習と事後ディスカッションを通じて、我々の生活を支える食・環境・生命について体験的に学ぶことを目的としたアクティブ・ラーニング科目である。
ダイバーシティ社会の中の男女共同参画/Gender Equality in Diversity Society
- 担当教員名 川面 充子(ダイバーシティ研究環境推進本部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜5-6時限
- 時間割コード G845279
- 単位数 2
- 授業の内容
日本は人口減少、少子高齢化による生産年齢人口不足が深刻となっている。また、産業化、技術革新による変化に伴い、社会のニーズや個人のライフスタイルの多様化している。このような背景を踏まえ、なぜ男女共同参画やダイバーシティ(多様性)を推進する必要があるのか、歴史的背景や日本の現状を理解するとともに、自分たちの暮らしている地域の現状と課題について考察する。
ダイバーシティ社会の中の男女共同参画 フィールドワーク編/Gender Equality in Diversity Society (Fieldwork)
- 担当教員名 川面 充子(ダイバーシティ研究環境推進本部)
- 学期・曜日時限 前期 集中
- 時間割コード G845282
- 単位数 2
- 授業の内容
座学で学んだテーマに即した場所を訪問し、直接観察したり関係者に聞き取り調査などを実施し、その結果をグループワークでまとめ発表、若しくはレポートを提出する。
Iより始めよ/Start with the First Step
- 担当教員名 岩井 秀和(工学部)
- 学期・曜日時限 後期 木曜7-8時限
- 時間割コード G845340
- 単位数 2
- 授業の内容
大学生活の中で、自信が持てない、積極的に行動できない、理解できない講義が多い、などと思っており、これらを何とかしたいと強く望む人のための、「自律性」を目指す実践プログラムです。単なるスキルアップ(how to型)の授業ではありません。また、いわゆる自分探しの授業でもありません。自分と世の中をそれぞれ客観的に認識することを目指します。毎週、思考し、かつ手足口を動かします。
アカデミック・スキルズ/Academic Skills
- 担当教員名 石井 和也(基盤教育)
- 学期・曜日時限 前期 水曜5-6時限
- 時間割コード G845348
- 単位数 2
- 授業の内容
この授業では,大学での学びにおいて必要不可欠な,聞く力/読む力/書く力/話す力の養成を行います。具体的には,講義の聞き方,文献の読み方,論理的な文章を書く方法,プレゼンテーションおよびディスカッションの方法など,4年間の大学生活の様々な場面で求められる,学習の基盤となる力の養成です。このような力は従来から,講義やゼミに参加し,課題の提出や発表を行う際に求められてきたものですが,現在は社会に出た後もこれらの力がより一層強く求められています。
皆さんの宇都宮大学での学びを充実させるだけではなく,社会に出た後も活用できる力を身につけることが本授業の目的です。本授業を通じて,大学生活4年間にとどまらず,長期的に必要となる力を確実に身につけましょう。
大学教育と学士力/Higher Education and Graduate Attributes
- 担当教員名 石井 和也(基盤教育)
- 学期・曜日時限 後期 火曜3-4時限
- 時間割コード G845350
- 単位数 2
- 授業の内容
この授業では,まず,急激な変化を見せる社会環境や自然環境の中で,変化に飲み込まれることなく確かな足取りで生き抜いていくための力について学びます。その後,各自の興味関心に沿って現代社会における問題を自由に取り上げ,研究を行うことで,これからの社会で必要となる能力を身につけていくためのきっかけを提供します。
近年,「学士力」という言葉がしばしば使われるようになってきました。学士力は,「知識・理解(知識の体系的な理解)」,「汎用的能力(コミュニケーション・スキル,数量的スキル,情報リテラシー,論理的思考力,問題解決力)」,「態度・志向性(自己管理力,チームワーク・リーダーシップ,倫理観,市民としての社会的責任,生涯学習力)」,「統合的な学習経験と創造的思考力(自らが立てた新たな課題を解決する能力)」を主な内容とし,大学を卒業するまでに習得するべき能力とされています。これらの能力は,不確実,不安定,曖昧になってきている世界の中で生きていくために不可欠の能力と言えるでしょう。
というのも,既存の知識体系を学ぶだけでは,経済や政治の急速な変化や,現在の社会にはまだ存在しない職業への対応ができないからです。皆さんが大学を卒業した後には,まったく想定外の社会状況や,まったく新しい職業や働き方が誕生しているかもしれません。大学4年間で学んだ知識体系だけでは変化に対応できないかもしれません。そのときに,たとえ社会が激変したとしても,その変化に対応し生き抜いていくために,論理的思考力や問題解決力,自己管理力や生涯にわたって学び続ける力,新たな課題に立ち向かい解決する力が必要となるのです。
したがって,本授業では,現代社会の潮流と,その潮流に応じて大学がどのような変化を見せてきたのかということを概観し,大学生である皆さんが身につけるべき能力を明らかにします。その後,具体的な課題を各自取り上げ,研究を進める際の能力を身につけるきっかけを提供します。
不安を減らし大学の講義が楽しくなるために必要なこと/What You Need to Manage Your Worries and Get Interested in University Lectures
- 担当教員名 岩井 秀和(工学部)
- 学期・曜日時限 前期 火曜7-8時限
- 時間割コード G845602
- 単位数 2
- 授業の内容
大学で学ぶ上で、講義内容が理解しやすくなるために必要なことを行います。言葉と図解による概念の理解の仕方、各自のイメージを描画し説明する、単調作業による非認知力の強化など、「自律性」を伸ばすための実践プログラムです。単なるスキルアップの授業ではありません。毎週、体を動かす内容になっています。
ものづくり体験/Problem Based Learning
- 担当教員名 渡邊 信一(工学部)
- 学期・曜日時限 後期 木曜9-10時限
- 時間割コード G845678
- 単位数 2
- 授業の内容
本授業では「ものづくり」を通して、ものづくりのセンス、ものづくりの精神、問題発見と解決能力、そして最も大切な、新しいものを創りだす創造性を身に付けることを目的とし、特に専門知識を必要としない「ものづくり」の製作体験をする。受講生は設定されたテーマに取組み、グループで自主的に「問題発見」「設計」「製作」「評価」をし、成果の「発表」を行うことを目的としたアクティブ・ラーニング科目である。
宇大を学ぶ~たかがパンキョウされどパンキョウ~/Learning about UDAI
- 担当教員名 石井 和也(基盤教育)
- 学期・曜日時限 前期 火曜3-4時限
- 時間割コード G845911
- 単位数 2
- 授業の内容
この授業では、様々な特色を持つ宇大での学び方について考えてみます。グループで学習活動を行うことで「宇大に入って良かった」と思えることを増やしていきましょう。今後の学生生活において重要となる学生同士の学び合い(ピア・サポート)についても理解を深め、その方法としてファシリテーションという話し合いの進め方を実践的に学びます。
日本の高等教育の歴史や基盤教育を学ぶ意義を理解し、さらに宇大生活を送るうえでの悩みや疑問を出し合いながら、それらに対応した理想のシラバスを作成します。そして学生、教員、職員による意見交換を行い、学生が主体的かつ効果的に学ぶためにはどうしたら良いかについて考えます。
実践データサイエンス/Practical Course of Data Science
- 担当教員名 吉田 聡太(基盤教育)
- 学期・曜日時限 後期 月曜5-6時限
- 時間割コード G846205
- 単位数 2
- 授業の内容
身の回りにある種々のデータから価値ある情報を抽出し課題解決や意思決定に活かす、といった「データサイエンス」のエッセンスを学習します。授業では、あらゆる専攻の学生に関係したトピックを題材に、データの分析はもちろん、身の回りの家電やスマートホンなどで活用されているAI・機械学習と称される技術の概要を説明しながら一部体験して頂いたり、日々の学業・仕事などで直面する煩雑な繰り返し作業やデータ収集の自動化、実験・フィールドワークの計画(意思決定)など、発展的な内容についてもご説明します。
授業の雰囲気が知りたい方は下記ホームページから授業動画(Youtubeへのリンク)をご覧ください。https://sites.google.com/view/syoshidant/講義の情報
生命保険を考える~ぜひ知ってほしい役割・商品・業界~/Life insurance, Health insurance and Pension~The markets and how it supports your life~
- 担当教員名 萩田 繁(その他)
- 学期・曜日時限 前期 火曜7-8時限
- 時間割コード G846206
- 単位数 2
- 授業の内容
この授業では、まずは、私達を取り巻く環境について概観する。その理解の上に立ち、少子高齢化社会の一層の進展により、表面化している社会保障制度の諸課題を背景に、生活設計の立て方、公的保障と私的保障の多様なあり方や私的保障(生命保険)の意義、自助努力の必要性や有用性について理解し、考察を深めて行く。また、近年における生命保険会社の活躍フィールドや隣接業界の取組についても触れ、業界研究の側面としての知識も深めることが出来る。
防災・安全教育/Disaster and Safety Education
- 担当教員名 青山 雅史(群大)(共同教育学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜3-4時限
- 時間割コード G847100
- 単位数 2
- 授業の内容
おもに学校における事故や災害による被害・被災事例をとりあげ、それらの実態について理解を深め、教職員が身に付けるべき学校安全や防災に関する基礎教養を提供する。
※共同教育学部のみ履修可
言語と教育/Language and Education
- 担当教員名 河内 昭浩(群大)(共同教育学部)
- 学期・曜日時限 前期 火曜7-8時限
- 時間割コード G847110
- 単位数 2
- 授業の内容
オムニバス形式で開設する。言語学、英語教育、国語教育のそれぞれの担当者の学問分野の専門性に基づいて、学習指導をする際に必要な、言語と教育に関する基礎的知識や考え方を講義する。また必要に応じて話し合いや発表などの言語活動を行う。
※共同教育学部のみ履修可
ジェンダー論(基盤教育科目)/Gender Studies
- 担当教員名 斎藤 周(群大)(共同教育学部)
- 学期・曜日時限 後期 火曜7-8時限
- 時間割コード G847120
- 単位数 2
- 授業の内容
教員になる上で知っておくべきジェンダー問題を検討する。
※共同教育学部のみ履修可
エスニック・マイノリティの子どもと教育/Education for Ethnic Minority Children
- 担当教員名 新藤 慶(群大)(共同教育学部)
- 学期・曜日時限 後期 木曜3-4時限
- 時間割コード G847130
- 単位数 2
- 授業の内容
はじめに、在日ブラジル人児童生徒の教育と保育をめぐる状況を、制度の展開と、子ども・保護者・教師(保育者)それぞれの視点から捉える。続いて、先住民児童生徒の教育について、アイヌ民族と、サーミ民族の事例をもとに、実態を把握する。さらに、外国人児童生徒貧困の問題について触れたうえで、最後に、外国人児童生徒教育を支える家庭-学校間の関係について考察する。
※共同教育学部のみ履修可