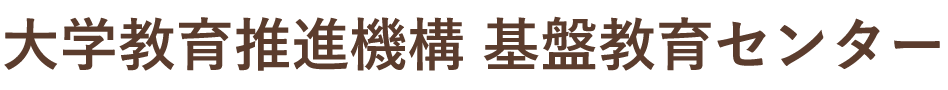自然科学系科目
電気電子数学入門/Introduction to Electrical and Electronic Mathematics
- 担当教員名 東 剛人(工学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜9-10時限
- 時間割コード G506000
- 単位数 2
- 授業の内容
基盤工学科の学生にとって必須である数学科目の学習は,1年次の基礎微積分学から始まります。これと同時進行する本講義では,上記数学科目を履修する上で土台となる数学の知識を学びます。さらに,基礎物理学で学ぶ運動方程式の解法を学びます。運動方程式の解法は電気電子分野の現象を理解する際に必要となります。
物理学入門/Introduction to Physics
- 担当教員名 夏目 ゆうの(教育学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜3-4時限
- 時間割コード G510517
- 単位数 2
- 授業の内容
「力学」、「熱力学」、「波動」、「電場・磁場」に関する基礎的な事項を簡単な実験を通して学ぶ。
家庭の中の物理/Physics at home
- 担当教員名 湯上 登(工学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜3-4時限
- 時間割コード G510560
- 単位数 2
- 授業の内容
現代社会で用いられている科学技術のうち,物理学を用いているものについて,その基礎的な物理現象を理解する
エレクトロニクス科学史/History of Electronics
- 担当教員名 入江 晃亘(工学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜3-4時限
- 時間割コード G512340
- 単位数 2
- 授業の内容
エレクトロニクスは,現代社会を支える重要な基盤であり,将来にわたって人々が豊かな社会生活を営むために不可欠なものである.本講義では,エレクトロニクスの歴史を概観することにより,如何にして新しい技術が誕生したか,また,その意義について解説する.
バイオミメティクス入門/Introduction of Biomimetics
- 担当教員名 中林 正隆(工学部)
- 学期・曜日時限 後期 金曜7-8時限
- 時間割コード G512345
- 単位数 2
- 授業の内容
生物が持つ高度な機能や製造過程を模倣して,技術開発に活かす学問領域バイオミメティクス(生物模倣技術)に関して体系づけて解説します.基本的な生物の組織構造から地球環境全体から見た「技術体系」,そしてこの学問領域の研究・市場動向,生物が進化によって得てきた効率的な動きや構造がいかに技術開発に用いられているのかを学ぶ.
ガリレオの静力学/Galileo's Statics
- 担当教員名 髙山 善匡(工学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜1-2時限
- 時間割コード G512350
- 単位数 2
- 授業の内容
イタリアの物理学者・天文学者・哲学者であるガリレオ・ガリレイは、天秤あるいは梃子(てこ)の釣合い原理のみを用いて、梁(はり)の強度論を展開させた。本講義では、釣合い原理と幾何学的手法で展開されるガリレオの静力学を学び、現代科学の基礎となった理論体系の端緒を理解する。
物質・材料の機器分析入門/Introduction to Instrumental Analysis
- 担当教員名 松本 太輝(地域創生推進機構)
- 学期・曜日時限 前期 水曜7-8時限
- 時間割コード G525577
- 単位数 2
- 授業の内容
大学の研究室や分析の現場に常備されているような汎用型の分析機器を多数取り上げ、各機器に対して原理、機能、特徴などを横断的に概括する。
ノーベル化学賞周辺の化学/Chemistry related to Nobel Prize in Chemistry
- 担当教員名 横田 信三(農学部)
- 学期・曜日時限 後期 月曜1-2時限
- 時間割コード G525605
- 単位数 2
- 授業の内容
ノーベル化学賞に関連した化学における重要な知見や分析手法を講義で説明し、また、2つの主要な化学機器分析法を実習を通して説明する。
化学プロセス工学入門/Introduction to Chemical Process Engineering
- 担当教員名 佐藤 正秀(工学部)
- 学期・曜日時限 後期 金曜3-4時限
- 時間割コード G525611
- 単位数 2
- 授業の内容
化学に限らず、バイオ、エレクトロニクス、自動車に至る各種工業生産に関わる製造プロセスの中では、ものを分ける・流す・反応させる・他のものとの熱の授受などの操作が数多く行われています。この授業では、工業生産に関わる製造プロセスで発生している各種現象を説明できる化学・プロセス工学の基礎を、地域における例を上げつつ学んでいきます。
香り・毒・兵器(やり直し高校化学→大学教養の化学)/Introduction of chemistry
- 担当教員名 大庭 亨(工学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜3-4時限
- 時間割コード G525612
- 単位数 2
- 授業の内容
どうやら化学は「むやみやたらと暗記させる嫌な科目」と思われているらしい。しかし、化学は「物質の科学」であり、世界のあらゆる物事を理解するための基礎の一つだ。例えば、スマホは物質でできているし、ウイルスもヒトも物質でできている。地球温暖化には物質の視点が不可欠だし、水や石油や希少金属をめぐる紛争もそうである。美術品の修復も、発掘品の年代測定も、科学捜査も物質の科学だし、ブラックホールに吸い込まれているガスも物質である。そこでこの科目では、高校化学や受験化学をめぐる嫌な思い出をリセットし、21世紀を創る大学生にふさわしい「物質の科学の視点」を身につけることを目標とする。化学が苦手な人も、化学を思い出せない人も歓迎です。
人間生活と植物/Human Life and Plants
- 担当教員名 山根 健治(農学部)
- 学期・曜日時限 後期 木曜1-2時限
- 時間割コード G532234
- 単位数 2
- 授業の内容
私たちの生活となじみが深い 植物たちのルーツを探り、森林資源保護と地球温暖化、食料の安全性を脅かす放射線対策、食糧資源としての植物の重要性と世界的な需給関係、農業とバイオテクノロジーなどを取り上げます。また、暮らしに潤いや彩を与える「くだもの」と「花,庭園,市民農園」などをテーマに実例を紹介しながら機能的特徴と文化的側面について解説します。植物の持つ特性やそれを利用発展させる農業、造園などを総合的に学んでもらいます。
21世紀を支える熱帯植物/Tropical Plants for the Sustainable World in the 21st Century
- 担当教員名 福井 糧(農学部)
- 学期・曜日時限 後期 火曜3-4時限
- 時間割コード G534255
- 単位数 2
- 授業の内容
熱帯地域は地球の全陸地の約38%を占め、世界人口の約半数が生活しているが、現在熱帯地域での人口が急速に増加し、それに伴い様々な環境破壊や生物資源の消失が進んでいる。このような状況をふまえ、熱帯植物資源が今後私達の生活にどのような影響を及ぼすかを考えるために、様々な熱帯植物についての基礎的な形態・生理を学び、各々の植物が資源としてどのように利用されてきたか/いるかについて、その歴史的意義を含めて学習する。また授業では、最近日本でも問題となっている「麻薬」と「麻薬植物」について特集し、薬物の薬理作用と人間による利用の歴史についてビデオを視聴して学習して、麻薬や「危険ドラッグ」が個人に及ぼす作用と現代における社会的弊害について考察する。
野外における野生動物識別テクニックの基礎/The Basics of Animal Tracks and Birds Identification
- 担当教員名 小寺 祐二(雑草管理教育研究センター)
- 学期・曜日時限 前期 火曜3-4時限
- 時間割コード G535333
- 単位数 2
- 授業の内容
日本では,人間と野生動物との軋轢が激化する一方で,絶滅に瀕した種が存在するなど,自然に関連する事象が社会問題として注目されつつあります.こうした問題の本質を理解するためには,日本の自然に何が起きているのかを認識できる技術が必要です.本講義では,自然の変化を捉えるために欠かせない野生動物識別技術についての基礎を解説します.
ウイルスの世界と生物の世界/The world of viruses, and the world of living things
- 担当教員名 岩永 将司(農学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜5-6時限
- 時間割コード G535340
- 単位数 2
- 授業の内容
本講義では、我々ヒトを含む「生物」と、風邪などの主な原因である「ウイルス」について、そもそも生物やウイルスとは何なのか、生物とウイルスの関わりは病気だけなのか、ワクチンとは何なのかといった疑問について幅広く概説します。
C言語・プログラミング入門/Introduction to C Language and Programming
- 担当教員名 倪 永茂(国際学部)
- 学期・曜日時限 前期 水曜3-4時限
- 時間割コード G540114
- 単位数 2
- 授業の内容
パソコン,ゲーム機,携帯電話等,ソフトウェア無しでは機能しない機械が身の回りにいっぱいあります.本授業では,ソフトウェアの作成に欠かせないプログラム言語の一つ,C言語について,多くの課題をこなすことにより,その基礎知識や基本文法を学びます.C言語の影響を受けた言語が数多くあるので,C言語をマスターすれば,他言語の習得にも役立ちます.
プログラミング応用/Applied Programming
- 担当教員名 横田 隆史(工学部)
- 学期・曜日時限 前期 月曜3-4時限
- 時間割コード G540912
- 単位数 2
- 授業の内容
コンピュータの使い方を覚えても,コンピュータについて学んだことにはならない.この科目では,プログラミングの側面からコンピュータへの理解を深め,能動的に使う姿勢を養う.そのために,まずプログラミングの初歩を学んだうえで,実社会の中での我々とコンピュータとの係わりについて学んでいく.
グラフィックス入門/Introduction to Computer Graphics
- 担当教員名 森 博志(工学部)
- 学期・曜日時限 後期 金曜9-10時限
- 時間割コード G540955
- 単位数 2
- 授業の内容
コンピュータグラフィックス(CG)に関する講義と,CG制作ソフトウェアによる3次元世界の記述の作成実習からなります.中間と期末の2回に分けて制作した作品の発表会を行います.
インターネットのしくみ/The Basics and Fundamentals of the Internet
- 担当教員名 三原 義樹(総合メディア基盤センター)
- 学期・曜日時限 後期 月曜9-10時限
- 時間割コード G541000
- 単位数 2
- 授業の内容
インターネットの基本的な「しくみ」を習得し,世界の情報通信について実例を通じて理解を深めます。
インターネットのしくみ/The Basics and Fundamentals of the Internet
- 担当教員名 三原 義樹(総合メディア基盤センター)
- 学期・曜日時限 後期 木曜9-10時限
- 時間割コード G541001
- 単位数 2
- 授業の内容
インターネットの基本的な「しくみ」を習得し,世界の情報通信について実例を通じて理解を深めます。
Webのしくみ/The Basics and Fundamentals of the World Wide Web
- 担当教員名 永井 明(総合メディア基盤センター)
- 学期・曜日時限 後期 月曜7-8時限
- 時間割コード G541005
- 単位数 2
- 授業の内容
World Wide Web(ワールドワイドウェブ)の基本的な「しくみ」を習得し、世界の情報通信について実例を通じて理解を深めます。
Webのしくみ/The Basics and Fundamentals of the World Wide Web
- 担当教員名 永井 明(総合メディア基盤センター)
- 学期・曜日時限 後期 木曜7-8時限
- 時間割コード G541006
- 単位数 2
- 授業の内容
World Wide Web(ワールドワイドウェブ)の基本的な「しくみ」を習得し、世界の情報通信について実例を通じて理解を深めます。
身のまわりのICT/ICT in Our Daily Life
- 担当教員名 三原 義樹(総合メディア基盤センター)
- 学期・曜日時限 後期 火曜5-6時限
- 時間割コード G541255
- 単位数 2
- 授業の内容
身のまわりにあり,私たちの生活や社会を支えている ICT について,幅広い事例学習を通じ,その基本的なしくみを習得するとともに,ICT 関連企業が求める人材像や栃木県内の ICT 企業の活動・方向性を学びます。
ワイヤレス通信のしくみ/Fundamentals of Wireless Communication Systems
- 担当教員名 古神 義則(工学部)
- 学期・曜日時限 後期 金曜1-2時限
- 時間割コード G541260
- 単位数 2
- 授業の内容
携帯電話に代表されるワイヤレス通信システムの基本をやさしく紹介します。また簡単な通信システムを作製するという実習も用意します。(受講生の数によっては実施できない場合があります)
ICTを活用した教育の理論と実践/Theory and Practice of Education Utilizing ICT
- 担当教員名 川島 芳昭(教育学部)
- 学期・曜日時限 前期前半 水曜7-8時限
- 時間割コード G541270
- 単位数 1
- 授業の内容
中・高等学校の全ての教員に必要なICTを活用した教育の意義やなぜ必要なのかを理論的に解説します。また,ICTを活用した授業設計の方法や注意点などについて具体的に解説します。
身近な気象学/Shorter Meteorology
- 担当教員名 髙橋 行継(農学部)
- 学期・曜日時限 後期 月曜3-4時限
- 時間割コード G554443
- 単位数 2
- 授業の内容
本講義は気象学を専門にする学生対象ではなく、それ以外の大多数の学生向けの気象学である。本来、気象学は物理学の一分野であることから、数式がたくさん出てきて難しいイメージがある。本授業ではこのような堅苦しさを取り払い、天気図、天気予報や身近な天気変化、大きな社会問題である地球温暖化などに焦点をあてて、「実生活に役に立つ」気象学を解説することに努める。全学部、全学年が対象の基盤教育科目であり、例年、文科系学生の受講も少なくない。スライドを利用した解説を中心に、所属学部にとらわることなくわかりやすい説明を心がけている。
健康のためなら死んでもいい!?/I would risk my life for my good health!?
- 担当教員名 吉澤 史昭(農学部)
- 学期・曜日時限 前期 木曜5-6時限
- 時間割コード G560022
- 単位数 2
- 授業の内容
若く活気のある時期には、あまり健康について意識しない。健康を失いかけたり、年齢とともに体の不調を感じ始めると、人は初めて健康を意識する。誰しも健康であり続けたいと願うのは当然である。しかし、なかには過剰に健康を意識するあまり、健康を害している訳でもないのに、我々を取り巻く様々な情報に踊らされて、健康維持のために多大なお金とエネルギーを費やす人が多く見受けられる。本講義では、栄養学の視点に立って、栄養に係わるいくつかのテーマを取り上げ、日常生活のなかで健康維持と栄養について考える場合の基本的なアプローチの方法を学ぶ。
創造ものづくり入門
- 担当教員名 松原 真理(教育学部)
- 学期・曜日時限 後期 不定時
- 時間割コード G560044
- 単位数 2
- 授業の内容
ものづくりを通し創造力の重要性を学ぶ。
人間の感覚を測る/Measurement of Human Feeling
- 担当教員名 渡邊 信一(工学部)
- 学期・曜日時限 前期 月曜9-10時限
- 時間割コード G580000
- 単位数 2
- 授業の内容
この授業では「人間の感覚」をテーマに実際に受講生たち自らが考えた実験を行い,この実験から得られたデータに対して,統計的手法を用いて分析を行います.その結果を考察し,発表してもらいます.この授業はグループワークによる実験の計画立案,実施,分析,考察を行いこれらの一連の作業を通して,受講生間のコミュニケーション能力,自主性の育成,統計学の実践的応用例の体験を目的としたアクティブラーニング科目です.
生物の多様性とは何か/What is Biodiversity
- 担当教員名 西尾 孝佳(雑草管理教育研究センター)
- 学期・曜日時限 後期 月曜5-6時限
- 時間割コード G580030
- 単位数 2
- 授業の内容
環境破壊の中でも,回復が最も難しいのが生物多様性の破壊です。野生で生活する個体が失われると,その個体群を回復させるのは非常に困難で,絶滅すれば,その種は二度と戻りません。人間は生態系がもたらす様々なサービスに完全に依存していて,そのサービスの相当部分を生物多様性がもたらしています。本講義では,「生物多様性を失うと,こうしたサービスも失われるのか」という問いかけに応じた様々な研究事例と,それらから得られた知見を平易に紹介します。
雑草観察入門/Introduction to Field Methods in Weed Science
- 担当教員名 西尾 孝佳(雑草管理教育研究センター)
- 学期・曜日時限 前期 水曜3-4時限
- 時間割コード G580037
- 単位数 2
- 授業の内容
私たちの身の回りには様々な種類の雑草が暮らしており,その観察は最も手軽に自然や多様性を感じられる手段の一つです。この手軽さから,雑草は生態や進化を研究する材料として古くから利用され,多くの知見が蓄積されてきました。本講義では,大学キャンパスに生育する雑草を観察材料として用い,植物の生態と進化,そしてそれらに及ぼす人の役割について学びます。
建設・建築工学入門/Introduction to Civil and Architectural Engineering
- 担当教員名 清木 隆文(地域デザイン科学部)
- 学期・曜日時限 後期 金曜3-4時限
- 時間割コード G580050
- 単位数 2
- 授業の内容
建設工学(以降,土木工学)・建築工学は,社会基盤や建築・都市をデザインするための総合工学である.その総合工学を学習するには,まず自然科学を理解することが基本となる.それぞれの専門分野からゲストスピーカーを招き,専門分野の基礎および応用する対象をわかりやすく紹介し,解説する.
なぜ理科を学ぶのか/What is the purpose of learning science?
- 担当教員名 人見 久城(教育学部)
- 学期・曜日時限 後期 木曜3-4時限
- 時間割コード G580060
- 単位数 2
- 授業の内容
小・中・高校までに学んだ「理科」とは、何を目的とした教科であったのか。何を基盤に、何を習得することをめざしていたのか。本授業では、これらの問いに対する答えを探しながら、自然科学に対する理解と、科学・技術等とのつきあい方についての理解を深めることをめざす。
日本の稲作から見えてくる日本農業と農政/Japanese agriculture and agricultural administration analyzed from rice farming
- 担当教員名 髙橋 行継(農学部)
- 学期・曜日時限 後期 木曜1-2時限
- 時間割コード G580061
- 単位数 2
- 授業の内容
農学部生物資源科学科の3年生を対象とした専門科目、「作物生産技術学」をベースにした基盤教育科目である。この専門科目では稲以外の麦、大豆、ソバと栽培計画、気象災害、農薬、有機農業、種子生産など農業を取り巻く農業生産関連の技術を広く取り上げている。新年度から新規開講しる本講義では、この中から我が国の農業の「基幹作物」である稲作(コメ作り)を中心に取り上げる。
講義ではイネの形態や生理生態、栽培技術、あるいは行政(農政分野)などで用いられる専門用語をたくさん使うことになるが、専門分野以外の学生、特に人文・社会科学分野系の学生が十分に理解できるように言い換えたり、ゆっくりと丁寧に専門性の高い用語などを解説するように心がける。
食×SDGs/Food×SDGs
- 担当教員名 橋本 啓(農学部)
- 学期・曜日時限 後期 オンデマンド科目
- 時間割コード G580062
- 単位数 2
- 授業の内容
皆さんは、食べたいものを、食べたい時に、食べたいだけ食べることができる状況にあると思います。(もちろん100%ではないでしょうし、様々な理由で制限をしている人もいるでしょうが。)しかし、そのような状況は決して当たり前のものではありません。また、いつまでこの状況が続くのかも分かりません。本授業では、食に関して様々な観点から学び、科学的な理解を深めるとともに、社会的な問題点に関しても意識することができる見方・考え方を養うことを目指します。
データサイエンス基礎/Basic Course of Data Science
- 担当教員名 熊本 真一郎(基盤教育)
- 学期・曜日時限 後期 火曜3-4時限
- 時間割コード G580063
- 単位数 2
- 授業の内容
今日の社会は、情報通信技術や計測技術の発展により、あらゆる分野において多種多様な大量のデータで溢れています。そしてそれらのデータから価値ある情報を抽出し、予測、意思決定、自動化、最適化、課題解決等に活用する一連のプロセスは、一般に「データサイエンス」と呼ばれ、近年その重要性が広く認識されるようになりました。本科目では、データサイエンスの基礎となる『数理的思考に基づくデータ分析手法(Excel)』と『プログラミング(Python)の基礎』を講義と実習を併用した形式で学習します。また、数学に苦手意識のある人やプログラミングが未経験の人でも理解できるように、基礎的内容を重点的に解説します。
幼児期からの科学の学び/Learning Science from Early Childhood
- 担当教員名 出口 明子(教育学部)
- 学期・曜日時限 前期 木曜3-4時限
- 時間割コード G580070
- 単位数 2
- 授業の内容
この授業では,人が「科学」をどのように認知し,思考し,学んでいくのかについての講義を行います。